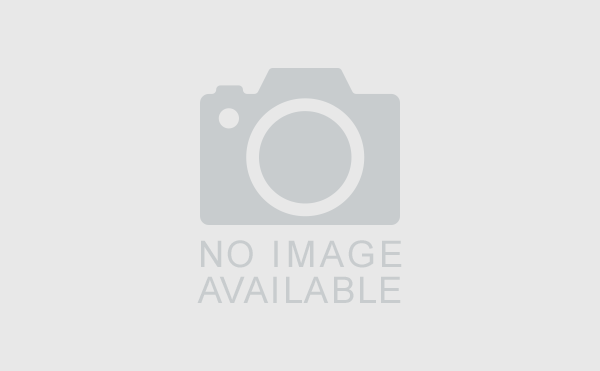33. コーシー・リーマンの定理(複素関数)
まず、導関数(複素関数)の公式をまとめておく。
導関数の公式
関数\(f(z),\;g(z)\)が微分可能であるとき、以下の公式が成り立つ。
1)\(\left\{f(z) + g(z)\right\}' = f'(z) + g'(z)\)
2)\(\left\{f(z) g(z)\right\}' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)\)
3)\(g(z) \neq 0\)であれば、$$\left\{\frac{f(z)}{G(z)} \right\}' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{\left\{g(z) \right\}^2}$$
4)\(\left\{g(f(z))\right\}' = g'((f(z))\cdot f'(z)\)
公式 4)合成関数の微分法則の証明(概略):
\(h(z) = g(f(z))\)とおく。\(h(z)\)の微分\(h'(z)\)は、微分の定義により次の極限として与えられる。$$h'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{h(z + \Delta z) - h(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{g(f(z + \Delta z)) - g(f(z))}{\Delta z} \quad \cdots (1)$$ここで、内側の関数\(f(z)\)の変化分を\(\Delta w\)とおく。$$w = f(z), \quad \quad \Delta w = f(z + \Delta z) - f(z)$$ 関数\(f(z)\)は微分可能(正則)であると仮定しているため、\(\Delta z \to 0\) のとき、\(\Delta w \to 0\)となる(微分可能であれば連続であるため)。式(1)の分子・分母に\(\Delta w\)をかけると、$$h'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \left( \frac{g(f(z + \Delta z)) - g(f(z))}{\Delta w} \cdot \frac{\Delta w}{\Delta z} \right)$$ここで、\(\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z)\)を代入し、変形する。$$h'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \left( \frac{g(w + \Delta w) - g(w)}{\Delta w} \cdot \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \right)$$ここで、極限の積の性質を利用し、2つの極限に分ける。$$h'(z) = \left( \lim_{\Delta z \to 0} \frac{g(w + \Delta w) - g(w)}{\Delta w} \right) \cdot \left( \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \right)$$さらに、それぞれの極限を考える。
・右側の極限: これは\(f(z)\)の微分の定義そのものである。$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = f'(z)$$
・左側の極限: \(\Delta z \to 0\)のとき\(\Delta w \to 0\)なので、この極限は\(g(w)\)の微分の定義となる。\(w\)は\(f(z)\) のことなので、$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{g(w + \Delta w) - g(w)}{\Delta w} = \lim_{\Delta w \to 0} \frac{g(w + \Delta w) - g(w)}{\Delta w} = g'(w) = g'(f(z))$$以上をまとめると合成関数の微分法則が導かれる。$$h'(z) = g'(f(z)) \cdot f'(z), \quad \quad \{g(f(z))\}' = g'(f(z)) \cdot f'(z)$$
コーシー・リーマン(CR)の定理
複素関数\(f(z)\)(\(z = x + j y\))を実部\(u(x, y)\)と虚部\(v(x, y)\)に分解し、$$f(z) = f(x + j y) = u(x, y) + j v(x, y)$$で表す。
【定理(必要十分条件)】
領域\(D\)(\(D \subset \mathbb{C}\))上で定義された複素関数\(f(z) = u(x, y) + j v(x, y)\)が領域\(D\)上で正則(複素微分可能)であるための必要十分条件は、次の2つが満たされることである。
1)\(u(x, y)\) と\(v(x, y)\)が\(D\)上で偏微分可能であり、かつ偏導関数が連続である(\(f(z)\)が\(C^1\)級である)。
2)以下のコーシー・リーマンの方程式が\(D\)上で成立する。$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{and} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$
\(C^k\)級(関数のなめらかさ)の定義
・\(C^0\)級:連続である。
・\(C^1\)級:1回微分可能で、導関数\(f'(x)\) も連続である。
・\(C^2\)級:2回微分可能で、2階導関数\(f''(x)\)も連続である。
・\(C^k\)級:\(k\)回微分可能で、\(k\)階導関数\(f^{(k)}(x)\)も連続である。
・\(C^\infty\)級:何回でも微分可能である。(例:指数関数\(e^x\)、三角関数\(\sin x\))
【正則性 \(\Longrightarrow\) CR方程式が成立する「必要条件」の証明の概略】
\(f(z)\)が点\(z = x + j y\)で微分可能であると仮定すると、その導関数 \(f'(z)\)は、\(\Delta z\)をどの方向から\(0\)に近づけても極限値が一意に定まるはずである。$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$ここで、\(\Delta z = \Delta x + j \Delta y\)とおき、次の2つの経路を考える。
・実軸に沿って近づける(\(\Delta z\)が実数)
\(\Delta z = \Delta x\)(\(\Delta y = 0\))として、\(\Delta x \to 0\)とする。$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(z + \Delta x) - f(z)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\{u(x + \Delta x, y) + j v(x + \Delta x, y)\} - \{u(x, y) + j v(x, y)\}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \left( \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + j \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$これは、 \(u\) と\(v\)の\(x\)に関する偏微分の定義そのものである。$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \cdots (1)$$
・虚軸に沿って近づける(\(\Delta z\)が純虚数)
\(\Delta z = j \Delta y\)(\(\Delta x = 0\))として、\(\Delta y \to 0\) とする。$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(z + j \Delta y) - f(z)}{j \Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\{u(x, y + \Delta y) + j v(x, y + \Delta y)\} - \{u(x, y) + j v(x, y)\}}{j \Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{1}{j} \left( \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta y} + j \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{\Delta y} \right) \end{aligned}$$ここで、\(\frac{1}{j} = -j\)を使って、 \(u\)と\(v\)の\(y\)に関する偏微分の定義を適用する。$$\begin{aligned} f'(z) &= -j \left( \frac{\partial u}{\partial y} + j \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= -j \frac{\partial u}{\partial y} - j^2 \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} - j \frac{\partial u}{\partial y} \cdots (2)\end{aligned}$$
\(f(z)\)が微分可能であるならば、(1)式 と(2) 式 の結果は一致しなければならない。各式の実部と虚部を比較し、$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{and} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$ が求まる。
【正則な例】指数関数\(w = f(z) = e^z\) が\(\mathbb{C}\)上で正則な関数であることをCRの定理を使って示す。
\(z = x + j y\)とおき、\(e^z\)を実部と虚部に分解する。$$f(z) = e^z = e^{x + j y}$$指数法則とオイラーの公式 \(\left(e^{j y} = \cos y + j \sin y\right)\)より、$$e^{x + j y} = e^x \cdot e^{j y} = e^x (\cos y + j \sin y) \\ = (e^x \cos y) + j (e^x \sin y)$$従って、実部: \(u(x, y) = e^x \cos y\)、虚部: \(v(x, y) = e^x \sin y\)
\(u(x, y)\)と\(v(x, y)\)を\(x\)および\(y\)で偏微分する。
$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y , \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y , \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$
また、\(u\)および \(v\)のすべての偏導関数 (\(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}\)) は、いずれも \(e^x, \sin y, \cos y\)の積であり、これらは実数平面上のすべての点 \((x, y)\)で連続である。
\(f(z) = e^z\)の実部と虚部はすべての点で連続な偏導関数を持ち、コーシー・リーマンの関係式を満たすため、\(f(z) = e^z\)は複素平面全体で正則である。
指数・三角関数の公式
指数・三角関数は複素平面上で正則であり、
$$(e^z)' = e^z , \quad (\sin z)' = \cos z , \quad (\cos z)' = - \sin z$$
【正則ではない例】\(f(z) = |z|^2\) (絶対値の 2 乗)の場合
\(f(z) = |z|^2\)は、原点\(z=0\)でのみ複素微分可能(正則)であり、その他の点では正則ではない。
\(|z|^2 = x^2 + y^2\)なので、実部\(u(x,y) = x^2 + y^2\)、虚部\(v(x,y) = 0\)である。従って、$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x , \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 2y , \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$ CRの定理より、$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Longrightarrow 2x = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Longrightarrow 2y = -0$$この連立方程式が満たされるのは、\(2x = 0 \quad \text{かつ} \quad 2y = 0\)つまり、原点 \((x, y) = (0, 0)\) のみである。
従って、\(f(z) = |z|^2\)は、原点\(z=0\)でのみ複素微分可能である。しかし、正則関数はある開領域全体で複素微分可能である必要があるので、この関数は正則関数ではない。
※複素関数が正則であるためには、単に実変数関数として微分可能であるだけでなく、コーシー・リーマンの関係式を満たし、実部と虚部の偏導関数が連続でなければならない。