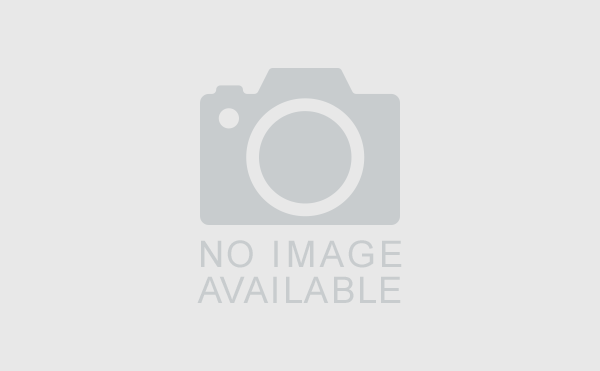32. 複素関数の微分(複素関数)
実関数における「微分」の役割は、関数のグラフを接線(1 次関数)で近似することで各点における関数の局所的な変化を表現するものである。複素関数の場合も同様で、関数はある点をある点に写すことになるのだが、その局所的な作用を1 次関数(比例関数)で近似することが「微分」の役割だといえる。
【例】関数\(w = f(z) = z^2\)の場合
\(f\)が\(z=j\)を\(w=-1\)に写す。\(z=i\)周辺の点が\(f\)によりどのように\(w=-1\)の周辺に写されるのかを見る。点\(j\)から\(z\)への差分は、\(\Delta z := z - j\)で、\(f(j)\)から\(f(z)\)への差分を\(w := f(z) - f(j)\)で定義する。すると、$$\Delta w = f(z) - f(i) = (j + \Delta z)^2 - (-1) = 2j \Delta z + \Delta z^2$$ \(\Delta z \approx 0 \)のとき、相対的に\(\Delta z^2\)の項は無視できるので、\(\Delta w \approx 2 j \Delta z\)を得る。\(2j = 2e^{j \pi/2}\) であるから、「\(\Delta w\) は(凡そ) \(\Delta z\)の長さを2 倍にし、90 度回転させたもの」だといえる。
微分可能性の定義
関数\(w = f(z)\)が\(z =\alpha\)で微分可能とは、ある定数\(A \in \mathbb{C} \)が存在し、$$\lim_{z \to \alpha} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} = A$$この定数\(A\)を\(f \)の\(\alpha\)における微分係数とよび、\(A = f′(\alpha)\) と表す。
【例】2次関数\(f(z) = z^2\)はすべての\(\alpha \in \mathbb{C}\)において微分可能であり、\(f'(\alpha)=2\alpha\)である。
\(f(z) = z^2\)として、複素数\(\alpha\)を固定すると、$$\lim_{z \to \alpha} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} = \lim_{z \to \alpha} \frac{z^2 - \alpha^2}{z - \alpha} =\lim_{z \to \alpha}(z + \alpha) = 2 \alpha $$となる。従って、\(z = \alpha\)で\(f\)は微分可能で、微分係数\(f'(\alpha)\)の値は\(2\alpha\)である。\(\alpha \in \mathbb{C}\)は任意なので、すべての複素数で\(f\)は微分可能である。
(注)\(z \to \alpha\)というのは、単に\(|z - \alpha| \to 0\)を意味する。ただし、その近づき方はまったく自由である。まっすぐでも、回転しならがらでも、ジグザグしながらでもよい。「考えうるあらゆる近づき方」を考慮しなければならない。
さて、複素関数\(f(z)\)の微分\(f'(z)\)の定義は、実関数\(f(x)\)の微分 \(f'(x)\)の定義と形式上は同じで、$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$である。しかし、複素数の世界では、この極限が存在するための条件が実関数の場合よりも厳しくなる。
実関数\(f(x)\)の場合、変数\(x\)が実数であるため、\(\Delta x \to 0\)の近づき方は、右から(\(\Delta x > 0\))と左から(\(\Delta x < 0\))の2通りしかない。このどちらから近づいても極限値が一致すれば微分可能である。
複素関数\(f(z)\)の場合、変数\(z = x + jy\)は複素数であり、複素平面\(\mathbb{C}\)上の点である。従って、\(\Delta z \to 0\)の近づき方は、複素平面上の無限の方向から考えられる。全ての方向から近づいたときの極限値が一致し、一意に定まるとき、その点\(z\)で微分可能(正則)であるという。このため、複素関数の微分可能性の条件は実関数よりも厳しい。
正則関数
微分可能性に条件を加えた「正則性」という条件を導入する。多項式、三
角関数、指数関数など、いわゆる「ふつうの関数」はすべてこの正則性をもっている。
導関数、正則関数の定義
複素平面\(\mathbb{C}\)の部分集合\(D\)(普通は開集合)にたいし、
・関数\(w = f(z)\)が\(D\)上で微分可能 \(\iff\)すべての\(\alpha \in D\)において\(f\)は微分可能。
・\(D\)上で微分可能な関数\(w = f(z)\) にたいし、点\(z \in D\) に微分係数\(f′(z)\) を対応させる関数を\(f\) の導関数とよぶ。
・関数\(w = f(z)\)が\(D\)上で正則 \(\iff\) \(f\)が\(D\)上で微分可能かつ導関数\(f′\)が\(D\)上で連続。
【正則な関数の例】
・\(f(z) = z^2\)は\(\mathbb{C}\)上で微分可能であり、導関数は\(f'(z) = 2z\)。これは連続なので、\(f\)は\(\mathbb{C}\)上で正則である。
・一般に多項式、指数関数\(e^z\)、三角関数\(\sin z,\;\; \cos z\)は\(\mathbb{C}\)上で正則である。有理関数も定義可能な範囲で正則である。
・一般に、正則関数の和差積商、合成、逆関数も定義可能な範囲で正則である。
微分可能ではない場合
複素共役を与える関数\(g(z) = \overline{z}\) は、すべての\(\alpha \in \mathbb{C}\)で微分可能でない。以下に証明例を示す。
微分可能であるためには、導関数の定義式における極限が、\(\Delta z\)がどの方向から0に近づいても同じ値に収束する必要がある。$$g'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{g(z + \Delta z) - g(z)}{\Delta z}$$これに\(g(z) = \overline{z}\)を代入する。$$g'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \overline{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{z} + \overline{\Delta z} - \overline{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$ここで、\(\Delta z = \Delta x + j \Delta y\)とおくと、\(\overline{\Delta z} = \Delta x - j \Delta y\)である。
1) 実軸上から近づける 場合(\(\Delta z\)が実数)
\(\Delta z\)を実軸上から 0に近づける。すなわち、\(\Delta y = 0\)とする。このとき \(\Delta z = \Delta x\)(実数)である。$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\overline{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \mathbf{1}$$
2) 虚軸上から近づける (\(\Delta z\)が純虚数)
\(\Delta z\)を虚軸上から0に近づける。すなわち、\(\Delta x = 0\)とする。このとき\(\Delta z = j \Delta y\)(純虚数)である。$$\lim_{\Delta y \to 0} \frac{\overline{j \Delta y}}{j \Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{-j \Delta y}{j \Delta y} = \mathbf{-1}$$異なる方向から0に近づけた結果、極限値が \(1\) と\(-1\)という異なる値になったため、極限\(\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}\)は存在しない。従って、関数\(g(z) = \overline{z}\)は複素平面上のどの点\(z\)においても微分可能ではない。