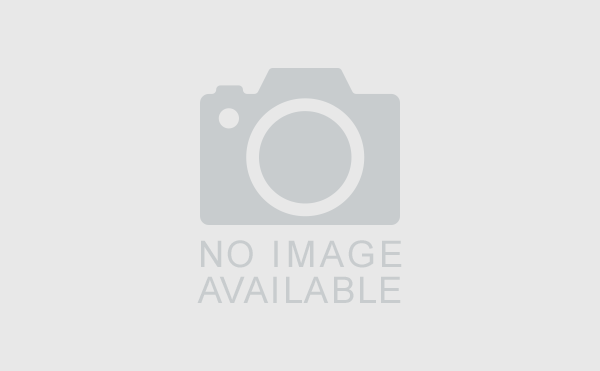31. 関数の極限と連続性(複素関数)
複素関数の極限は、実数関数の極限と基本的な考え方は同じであるが、複素数特有の性質があるため、より厳密な理解が必要である。
複素関数の極限の定義
\(z \in \mathbb{C}\)を変数、\(\alpha ,\beta \in \mathbb{C}\)を定数とする。
(1) 変数\(z\)が\(L = |z - \alpha| \rightarrow 0\)をみたしながら変化するとき、\(z \rightarrow \alpha\)と表す。
(\(L\)は\(z\)と\(\alpha\)の距離)
(2)「\(z \rightarrow \alpha\)ならば\(f(z) \rightarrow \beta\)」が成り立つとき$$ f(z) \rightarrow \beta \;\; (z \rightarrow \alpha) \text{もしくは} \lim_{z \to \alpha}f(z) = \beta$$と表し、\(\beta\)を\(f(z)\)の\(z \rightarrow \alpha\)における極限とよぶ。
※ (1)の\(|z - \alpha| \rightarrow 0\)は実数の意味なので、実数と同じ概念である。
複素極限の最も重要な性質 (経路独立性)
実数関数の極限\(\lim_{x \to x_0}\)では、1次元空間なので\(x\)は\(x_0\)に「左から」近づくか「右から」近づくか、の二通りの経路しかない。しかし、複素数平面上の点\(z\)が\(\alpha\)に近づく場合、2次元空間なのでその経路は無限に存在する(直線、曲線、渦を巻きながらなど)。
複素関数\(f(z)\)が\(\alpha\)で、極限\(\beta\)を持つためには、どの経路を通って\(\alpha\)に近づいたとしても、関数値\(f(z)\)が必ず同じ値\(\beta\)に収束しなければならないという条件が加わる。
「極限が存在する \(\iff\) どの経路からも同じ値に収束する」
もし、異なる二つの経路(例えば実軸に沿う経路と虚軸に沿う経路)で計算した極限値が異なれば、その点\(\alpha\)において極限は存在しないと結論づけられる。
実部と虚部による極限
\(z = x + jy, \quad z_0 = x_0 + j y_0 \quad (x,y,x_0,y_0 \in \mathbb{R})\) 、\(f(z) = u(x, y) + j v(x, y)\) と実部と虚部に分けて考えると、複素極限は次のように実数関数の二変数極限に分解できる。$$\lim_{z \to z_0} f(z) = L = L_1 + j L_2$$ $$\iff \begin{cases} \lim_{(x, y) \to (x_0, y_0)} u(x, y) = L_1 \\ \lim_{(x, y) \to (x_0, y_0)} v(x, y) = L_2 \end{cases}$$つまり、極限が存在するためには、実部\(u(x, y)\) と虚部 \(v(x, y)\)の両方が、二変数関数として同時に極限を持たなければならない。
複素関数の微積分においても、実部と虚部にわけることで必ず実関数の微積分に帰着できる。
\(|z - \alpha| = \sqrt{|x - a|^2 + |y - b|^2} \geq \sqrt{|x - a|^2} = |x - a|\)より、\(z \to \alpha \Rightarrow x \to a\)。同様にして、\(z \to \alpha \Rightarrow y \to b\)。三角不等式より、\(|z - \alpha| = |(x - a) + j(y - b)| \leq |x - a| + |y - b|\)が成り立つ。よって、\(x \to a\)かつ\(y \to b\)のとき、\(z \to \alpha\)。
三角不等式 \(|z| - |w| \leq |z + w| \leq |z| + |w|\)
まず、任意の複素数\(z\)と\(w\)に対し、三角不等式 \(|z + w| \leq |z| + |w|\)が成り立つことを考える。
三角不等式は、複素数平面上におけるベクトルの「長さ」に関する最も基本的な性質の一つで、\(|z|\)は複素数\(z\)の絶対値(原点からの距離)を表す。
複素数\(z\)と\(w\)を、複素数平面上の原点から引かれたベクトルと考えると、\(|z + w|\)はベクトル\(z\)とベクトル \(w\)を足し合わせた結果(合成ベクトル)の長さで、\(|z| + |w|\)は ベクトル\(z\)の長さとベクトル\(w\) の長さの和である。この不等式は、「三角形の二辺の長さの和は、残りの一辺の長さよりも大きい、または等しい」というユークリッド幾何学の原理を、そのまま複素数平面上のベクトルに適用したものに他ならない。等号 \(|z + w| = |z| + |w|\) が成り立つのは、\(z\)と\(w\)が同じ方向を向いている(複素平面上で一直線上に並んでいる)場合に限り、\(z\)と\(w\)の偏角が等しいか、または一方がゼロである場合である。
次に、\(|z| - |w| \leq |z + w|\)が成り立つことを考える。\(z = (z + w) + (-w)\)として、通常の三角不等式 \(|A + B| \leq |A| + |B|\) を適用する。ここで、\(A = z + w\)、\(B = -w\) と見なす。よって、$$|z| = |(z + w) + (-w)| \leq |z + w| + |-w|$$である。絶対値は符号に関係なく \(|-w| = |w|\) が成り立つので、\(|z| \leq |z + w| + |w|\)となる。この不等式の両辺から \(|w|\)を引き、$$|z| - |w| \leq |z + w|$$となる。
【公式】\(\lim_{z \to \alpha} f(z)=A, \quad \lim_{z \to \alpha}g(z) = B\)であるとき、以下が成立する。
(1) \(\lim_{z \to \alpha} \left\{f(z) + g(z) \right\} = A + B\)
(2) \(\lim_{z \to \alpha} f(z) g(z) = AB\)
(3) \(B \neq 0\)のとき、\(\lim_{z \to \alpha}\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B}\)
関数の連続性
連続性、連続関数の定義
・関数\(w = f(z)\) が\(z = \alpha\) で連続であるとは\(\lim_{z \to \alpha} f(z) = f(\alpha)\)が成り立つことをいう。
・複素平面\(\mathbb{C}\) の部分集合\(D\)にたいし,関数\(f\)が\(D\)の任意の点で連続であるとき、「\(f\)は\(D\)上で連続である」という。
・関数\(f(z)\)が定義できるすべての\(z =\alpha\)で連続であるとき、\(f\)を連続関数とよぶ。
【連続関数の例(2乗)】\(f(z) = z^2\) とし、\(\alpha \in \mathbb{C}\)を定数とする。\(z \to \alpha\)のとき、$$f(z) - f(\alpha) = z^2 - \alpha^2 = (z + \alpha)(z - \alpha)
\rightarrow 2\alpha \cdot 0 = 0$$が成り立つから、\(z = \alpha\)で連続である。\(\alpha\)は任意であるから、\(f(z) = z^2\) は\(\mathbb{C}\)上で連続な関数である。
【連則関数の例(指数関数)】複素指数関数\(e^z\)は、複素数\(z = x + jy\) (\(x, y\)は実数)に対して、$$e^z = e^{x+jy} = e^x (\cos y + j \sin y)$$と定義される。この定義から、\(e^z\)の実部\(u(x, y)\)と虚部\(v(x, y)\)は、
・実部: \(u(x, y) = e^x \cos y\)
・虚部: \(v(x, y) = e^x \sin y\) となる。
複素関数\(f(z)\)が点\(z_0\)で連続であるとは、\(\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)\)が成り立つことで、これは、実部と虚部の関数がそれぞれ連続であることと同値である。すなわち、複素関数\(f(z) = u(x, y) + j v(x, y)\)が\(z_0 = x_0 + j y_0\)で連続であるためには、実部関数 \(u(x, y)\)と虚部関数\(v(x, y)\)が、実2変数関数として点\((x_0, y_0)\)で連続である必要がある。\(f(z) = e^z\)の実部と虚部である\(u(x, y) = e^x \cos y\)と\(v(x, y) = e^x \sin y\)について考える。これらの関数は、すべて連続な実数関数の積で構成されている。
・\(e^x\): 実数\(x\)に関して連続な関数。
・\(\cos y\): 実数\(y\)に関して連続な関数。
・\(\sin y\): 実数\(y\)に関して連続な関数。
一般に、連続な実数関数の積は連続である。従って、
・実部\(u(x, y) = e^x \cos y\)は、実 2 変数関数として連続。
・虚部\(v(x, y) = e^x \sin y\)は、実 2 変数関数として連続。
実部\(u(x, y)\)と虚部\(v(x, y)\)がすべての\((x, y) \in \mathbb{R}^2\)で連続であるため、複素関数\(f(z) = e^z = u(x, y) + j v(x, y)\)は、複素平面\(\mathbb{C}\)全体で連続関数である。