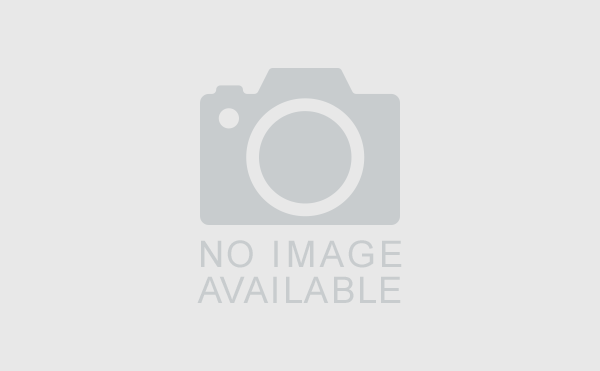27.指数関数(複素関数)
ド・モアブルの公式は、オイラーの公式を用いることで複素数の指数関数により簡単に導ける。
ド・モアブルの公式
ド・モアブルの公式は、任意の複素数\(z = \cos \theta + j \sin \theta \) と整数\(n\)に対して、次の関係が成り立つことである。$$(\cos \theta + j \sin \theta)^n = \cos(n \theta)+j \sin(n \theta)$$
この関係に複素数の指数関数と三角関数を結びつけるオイラーの公式を用いる。$$e^{j \theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$ここで、\(e\)はネイピア数、\(j\)は虚数単位、\(\theta\)は実数(単位:ラジアン)である。複素数\(z\)を極形式\(z=r(\cos \theta + j \sin \theta) \)で表したとき、オイラーの公式を使うと、指数関数を用いて、$$z = r e^{j \theta}$$と簡潔に表現できる。この\(z\)を\(n\) 乗すると(\(n\)は任意の整数)。$$z^n =r^n (\cos\theta + j\sin\theta)^n$$指数関数で表された形に\(n\)乗の計算を適用すると、指数法則により、$$z^n = (re^{j\theta})^n = r^n e^{j(n\theta)}$$これにオイラーの公式を使うと、$$r^n e^{j(n\theta)} =r^n(\cos(n\theta) + j\sin(n\theta))$$となるので、ド・モアブルの公式が成立することがわかる。
オイラーの公式
オイラーの公式 $$\boldsymbol{e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta}$$ は、異なる数学分野である指数関数と三角関数を複素数の世界で統一的に結びつけるという点で、極めて重要である。複素数\(z\)を表現する際に、三角関数を用いた極形式\(z = r(\cos\theta + j\sin\theta)\) は、オイラーの公式により複素指数関数表示 \(\boldsymbol{z = re^{j\theta}}\) へと簡潔に書き換えられる。 この指数表示により、複素数の乗算・除算・べき乗が、実数の指数計算と同じように指数法則を用いて容易に行えるようになる。オイラーの公式は、以下のように導出される。
マクローリン展開によれば、任意の実数\(x\)にたいして、$$e^{x} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots $$が成り立つ。ここで、\(x\)に純虚数\(j \theta (\theta \in \mathbb{R}) \)を代入すると、$$e^{j \theta} = 1 + \frac{j \theta}{1!} + \frac{(j \theta)^2}{2!} + \frac{(j \theta)^3}{3!} + \frac{(j \theta)^4}{4!} + \cdots \\ = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots \right) + j \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \right)$$となる。同じく実数について成立するマクローリン展開$$ \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots , \quad \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots $$より、オイラーの公式$$e^{j \theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$を得る。
オイラーの公式より、「複素数の指数関数」を以下のように定義する。
(指数関数)定義:複素数\(z = x + jy \; (x,\; y \in \mathbb R)\)にたいし、$$e^z \colon = e^x(\cos y + j \sin y)$$を対応させる関数を\(z\)の指数関数とよぶ。
指数関数\(e^z\)は、絶対値\(e^x >0\)、偏角\(y\)の複素数である。\(e^x > 0\)より、指数関数\(e^z\)は0にならないことに注意する。また、この定義はあくまで「指数関数\(e^z\)」という関数であり、「\(e\)の複素数\(z\)乗」ではない。
指数関数の性質
指数関数の重要な性質が「指数法則」と「周期性」である。
指数法則と周期性:すべての複素数\(z,w\)にたいして次が成り立つ。
1)\({e^z} \cdot {e^w} = e^{z+w}\)
2)\(\frac{e^z}{e^w} = e^{z-w}\)
3)\(e^{z+2\pi j} = e^z\) (指数関数は周期\(2\pi j\)の周期関数である。)
\(e^{2\pi j} = \cos {2\pi} + j\sin{2\pi}=1\)なので、\(e^{z+2\pi j} = {e^z} \cdot e^{2 \pi j} = {e^z} \cdot 1 = e^z\)である。とくに\(z=0\)の場合は、すべての整数\(m\)にたいして$$e^0 = e^{2\pi m j} =1$$が成り立つ。
指数法則の応用
【1の\(N\)乗根】自然数\(N\)にたいし、方程式\(z^N = 1\)の解を1の\(N\)乗根とよぶ。
極形式を用いて、方程式\(z^5 =1\)の解を\(z = re^{j \theta} \quad (r > 0, \; 0 \le \theta < 2 \pi) \)とおく。ド・モアブルの公式より、\(z^5 = r^5 e^{j 5 \theta} = 1\) が成り立つ。絶対値を比較することで、\(r =1\)なので、\(e^{j 5 \theta} = 1\) 。一方、¥(e^{2m j ¥pi}=1 ¥quad (m ¥in ¥mathbb Z) ¥)であるから、\(5 \theta = 2m\pi \)である。\(\le \theta < 2 \pi\)の条件から、\(\theta = \frac{2m \pi}{5} \quad (m=0,1,2,3,4)\)が得られる。以上より、1の5乗根は、\(e^{0},e^{2\pi j/5},e^{4\pi j/5}, e^{6 \pi j/5},e^{8 \pi j/5}\)の5個である。これらはすべて単位円上にあり、正5角形の頂点となる。同様な計算をすることで、一般に以下が成り立つ。
1の\(N\)乗根
\(N \in \mathbb N\)とするとき、方程式\(z^N =1\)の解は$$z=e^{\frac{2m \pi j}{N}} \quad (m=0,1,\cdots , N-1)$$の\(N\)個であり、これは1を頂点にもち単位円に内接する正\(N\)角形の頂点である。