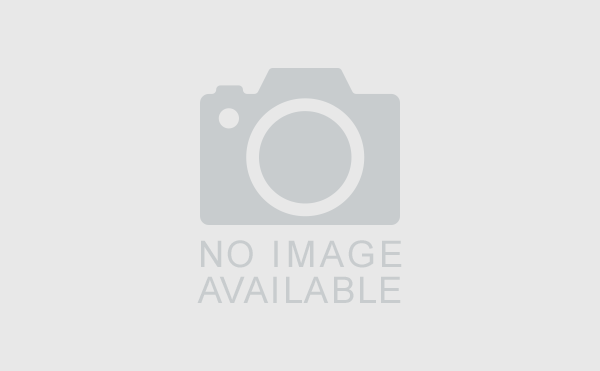14. 高松塚古墳と金峯山寺
奈良へ小旅行した。これまで、東大寺、興福寺、薬師寺などを参拝したことがある。今回は、1泊2日で吉野の金峯山寺を目指した。初日は、橿原神宮(写真1)を参拝して大和八木駅周辺のホテルで宿泊すれば良いと考えていたが、時間が余ったので、明日香村まで行ってみた。レンタカーが手配できなかったので、電車で移動して飛鳥駅で下車した。駅前にレンタサイクルがあったが、自転車はもう数十年乗っていないので、徒歩で高松塚古墳(写真2)を目指した。脊柱管狭窄症で痛む足を引き摺りながら向かっていたが、高松塚古墳への道が分からなくなった。飛鳥歴史公園館への道路際で交通量調査をしている人に尋ねると、道路下のトンネルを潜る必要があると教えられた。さらに、現在、高松塚古墳壁画仮設修理施設の見学会を開催していることを教えてくれた。予約制とのことなので、見学できないかも知れなかったが受付に向かってみた。すると、2名分キャンセルがあり、急遽見学できることになった。修理施設はガラス張りの部屋で空調が厳重にされた研究施設であった。古墳内部にあった石室が分解され、部屋に陳列されている。ガラス窓越しに双眼鏡で四神の玄武、白虎、青龍(朱雀は昔の盗掘で損壊)や女子群像の壁画を見学した。説明の方に尋ねたところ、壁画に描かれた絵の顔料、染料は大陸由来と推定されているが、研究中とのことで、蛍光X線による非接触計測で調査しているとのことだった。石室の壁画は1972年の発見以来、黴などで汚染されてきたため、この修理施設に移設して、黴の除去などが進められてきたとのことである。修理施設から高松塚古墳に向かい、その傍らにある高松塚壁画館で壁画や副葬品などのレプリカを見学した。実物を見てきたので、感動はやや薄れたが、良く再現されていた。
飛鳥駅からの往復は足に堪えたが、修理施設を偶然にも見学でき、充実した1日目であった。
2日目は、金峯山寺のロープウェイの1便を目指して大和八木駅を出発した。橿原神宮前駅で近鉄吉野線に乗り換えて吉野駅へ。吉野駅からは徒歩数分でロープウェイ 千本口駅に向かった。このロープウェイは日本最古のロープウェイ(1929年から稼働)で、そのためか出発、到着では、ゆらゆらとゴンドラが揺れ、乗降中は係の人がゴンドラを支えて揺れを止めていた。ロープウェイの吉野山駅から銅鳥居をくぐり徒歩で約500m先の金峯山寺へ向かった。金峯山寺(写真3)は、白鳳時代に役小角が一千日間の参籠修行し金剛蔵王大権現を感得され、修験道のご本尊とされて、寺を開創されたものとされている。現在では金峯山修験本宗の総本山として全国の修験者・山伏が集う修験道の中心寺院となっている。




現在、仁王門は大修理中のため拝観できなかった。また、金峯山寺の御本尊である金剛蔵王大権現は、秘仏のため春、秋だけご開帳されることになっており御簾に隠されていた。金剛蔵王大権現は、釈迦・観音・弥勒の三仏の化身とされており、日本独自の菩薩である。蔵王堂は拝観できるので、多くの尊像が安置されている堂内を一巡し、金剛蔵王大権現の御簾の前でお参りさせてもらった。金剛蔵王大権現を直接拝観することはできなかったが、金峯山寺聚法殿内に平成7年3月から「金峯山寺シアター」が開設されており、 VR映像「金峯山寺」(TOPPAN(株)制作)が公開されていた。金剛蔵王大権現が迫力ある綺麗な映像で紹介されている。
次に、境内の案内図にある頭脳の守護神という言葉に惹かれて、惚ける年齢に相応しいかと浅慮し脳天大神龍王院を参ることにした。この場所は、蔵王堂から下った谷合にあり、約500段の石段を下りる必要がある。途中、役行者銅像をお参りし、ひたすら石段を下った。昨日に続き、痛む足を引き摺っての行程となったなあと少し後悔した。石段の途中には倶利迦羅剣の像(写真4)もあった。勇者の剣みたいだなと軽口を叩きながら石段と格闘し続けた。ちなみに倶利迦羅剣は不動明王の剣である。足先だけでなく膝の痛みまで感じながら500段の石段を下りきり、脳天大神を参拝した。さて、帰り道はどうしたものかと脳天大神龍王院前の道路標識を見ると、この道から最寄りの駅は非常に遠いので、石段を戻るようにと書いてあった。Googleマップで見ると金峯山寺前の道まで4.3 kmである。再び、石段と格闘することになった。手摺に掴まり、手で体を引っ張り上げながら石段を登った。若い頃は、きつさを感じても気合を入れなおせば身体は動いていたが、気合では回復できない身体年齢をヒシヒシと感じながら、心臓が止まることなくどうにか登り着いた。
はてさて脳天大神のご利益は本編に反映されるか。